仏具とは、ご先祖さまや仏さまを祀る際に用いる道具の総称のことです。基本的に仏具は、仏壇を購入する際に一緒に揃えて購入しますが、仏具にはさまざまな種類があるため、どれが必要でどれが不要なのか判断に困る方も多いことでしょう。
今回の記事では、仏具の歴史や種類、使い方などについて解説します。
仏具が普及したのは江戸時代
仏具が一般家庭に普及したのは、江戸時代ごろだと言われています。それまではお寺で僧侶が使用するものでしたが、江戸時代に入ると仏壇が一般家庭にも普及するようになり、それに伴って仏具も広く使われるようになりました。
仏具の種類

現代主流の仏壇は省スペースでコンパクトなものが多くなっているため、仏具も必要最低限なものだけを揃える方が増えています。ここでは、以下の3カテゴリーにわけてご紹介します。
- ご本尊・脇侍、位牌
- 最低限必要な仏具
- あればなおよい仏具
①ご本尊・脇侍、位牌
ここでは、それぞれの役割や飾り方を解説します。
ご本尊(ほんぞん)=信仰の対象
ご本尊とは、仏教において信仰の対象となる仏さまを表したものです。仏像と掛け軸の2つのタイプがあり、仏像は立体的な形で仏さまの姿を表し、掛け軸には仏さまの絵画が巻かれています。どちらも仏壇の中央部に安置されます。
このご本尊は、宗派によって種類が異なります。
脇侍(わきじ・きょうじ)=各宗派の開祖
脇侍は、本尊の左右に配置される仏具のことを指し、各宗派の開祖や仏教に影響を与えた僧侶を祀ったものです。こちらもご本尊と同じように宗派によって異なります。
| 宗派 | 脇侍(左) | ご本尊 | 脇侍(右) |
| 浄土宗 | 法然上人 | 阿弥陀如来 | 善導大師 |
| 浄土真宗本願寺派 | 蓮如上人 | 阿弥陀如来 | 親鸞聖人 |
| 真宗大谷派 | 親鸞聖人※ | 阿弥陀如来 | 蓮如上人※ |
| 臨済宗 | 普賢菩薩 | 釈迦如来 | 文殊菩薩 |
| 曹洞宗 | 常済大師 | 釈迦如来 | 承陽大師 |
| 真言宗 | 不動明王 | 大日如来 | 弘法大師 |
| 日蓮宗 | 鬼子母神 ※ | 御曼荼羅・三宝尊・日蓮聖人 | 大黒天 ※ |
※お寺や地域によって左右の配置が異なる場合あり。
位牌(いはい)=故人の魂が宿るもの
位牌は戒名や没年月日が書き入れられたもので、故人の魂が宿るとされています。位牌を安置する場所は仏壇の右側です。
浄土真宗では位牌の代わりに、無地の掛け軸に故人の法名を書き入れた法名軸を使用します。
※位牌について詳しく知りたい方はこちら
お位牌について
②最低限必要な仏具

必要最低限の仏具として必要なものは、三具足(みつぐそく:香炉・燭台・花立)や仏飯器、茶湯器などです。使い方は以下の通りです。
香炉(こうろ)
香炉は、お線香を焚く際に使用する器です。器の中に灰を入れ、そこに火を灯したお線香を立たせます(※宗派によっては寝かせる場合もあり)。
仏教の教えでは、亡くなると現世の食べ物を食べることができず、香りを食べ物とする「香食(こうじき)」という考えがあります。お線香の煙は、仏さまやご先祖さまの食べ物であり、また現世とあの世をつなぐ道しるべの役割もあるとされています。そのため、毎日欠かさずお線香を灯すようにしましょう。
※お線香をあげる理由を詳しく知りたい方はこちら
お仏壇へ線香をあげる理由や注意点を徹底解説
燭台(しょくだい)
燭台は「火立(ひたて)」とも呼ばれている、ろうそくを立てるために必要な仏具です。
仏教の教えでは、ろうそくの炎は仏さまの「智慧」と「慈悲」を表します。暗闇を照らす「智慧」で人々の心の闇や無知を照らし、炎の熱で温める「慈悲」で人々を慰め救済すると考えられています。また、ろうそくの光は浄土へ旅立つための道しるべであり、お参りをする人が「ここにいます」と伝える役割も持っています。
花立(はなたて)
花立は、仏花を生けるための仏具です。
花立には仏花だけではなく、故人が好んだ花を供えてもよいとされています。お仏壇に花を供える理由は諸説ありますが、お線香の香りとともに花の香りを楽しんでいただくためお供えするという考え方や、「お釈迦様が前世で修行中に、仏さまへのお供えとして花を供えた」という逸話から現在の習わしに繋がったという考え方などがあります。
※仏花と墓花との違いを知りたい方はこちら
仏花と墓花は何が違う?仏花のタブーや飾り方もご紹介
おりん
おりんは、お経を唱える際や手を合わせる際に使用する仏具です。お椀型の鈴の形をしており、「おりん・りん座布団・りん台・りん棒」で1セットになっています。
おりんの涼やかな音色には、邪気を払う効果があるとされています。おりんは元々、禅宗のみで使用されていましたが、現在では宗派を問わず広く使われるようになりました。また、宗派によって名称が異なり、鏧(きん)・小鏧(しょうきん)・鐘(かね)と呼ばれることもあります。
※おりんを鳴らす回数について知りたい方はこちら
仏壇にあるリンを鳴らす回数に決まりはあるのか?
茶湯器(ちゃとうき)
茶湯器は、お茶やお水を供えるための湯呑みです。
浄土真宗では「極楽浄土には水が満ちている」と考られているため不要とされていますが、供養の気持ちで供える場合もあります。
仏飯器(ぶっぱんき)
仏飯器は、ご飯を供えるための仏具です。高い足が付いている伝統的な形のものから、現代的でモダンなデザインのものまで多くの種類があります。
前述した通り、仏さまは煙や香りを召し上がられるため、仏飯器に供えるご飯は炊き立てを一番最初に供えましょう。
③あればなおよい仏具

ここで紹介する仏具は、必須ではないものの持っていた方が供養やお参りがしやすくなるものです。
焼香炉(しょうこうろ)
焼香炉は、抹香(まっこう)を焚くための仏具です。お参りの際には灰の上に溝をつくり、そこに抹香を線状に敷いて火をつけます。
年忌法要を自宅で執り行う場合は準備しておくとよいでしょう。
お線香立て
お線香立ては、使用する前のお線香を保管しておくための仏具で、線香差しとも呼ばれています。一般的には、仏壇の上の香炉とセットで配置されます。
火消し
火消しは、仏壇で灯したろうそくの火を消すための仏具です。火消しを使用することで火災のリスクを減らすことができます。火消にはさまざまなデザインのものがあり、帽子型・トング型、うちわ型などがあります。
経机(きょうづくえ)
経机は、供物机(くもつづくえ)とも呼ばれる仏具で、本来は経本や経典を置くためのものですが、現在では香炉や花立、供物を置く場所として使われることが多くなっています。
お仏壇マット
お仏壇マットは、仏具の下に敷くマットです。最近は防炎加工されているものが多く出回っており、マッチやろうそく、線香の火による火災を防ぐことができます。またお供物による汚れから仏壇を守る目的もあります。
過去帳(かこちょう)
過去帳は、故人の法名や没年月日を記録する帳面のことで、見台と呼ばれる専用の台に置いて使用します。これは幅広い宗派で用いられているもので、家系図のような役割も果たします。
高杯(たかつき)
高杯は、脚付きの台の上に浅い皿が乗った仏具で、お菓子や果物を供えるために使用します。デザインや大きさは多種多様で、素材も陶器製、木製、黒檀、花梨などさまざまあります。高杯は、日常の供養から法要まで幅広く使用されるため、スペースに余裕があるのであれば揃えるとよいでしょう。
木魚(もくぎょ)
木魚は、読経のリズムを整えるための仏具です。なぜ木魚が魚を模しているかというと、目を瞑らない魚の習性から「寝る間を惜しんで修行に励む」という意味が込められているからです。ただし、真言宗や浄土真宗では使用しない場合もあります。
吊り灯篭(つりどうろう)
吊り灯篭は、天井から吊り下げて使用する仏壇を照らすための照明器具です。コンパクトな上置き型の仏壇ではあまり使用されず、ほとんどが大きな仏壇に設置されています。
瓔珞(ようらく)
瓔珞は、仏壇を飾る2個セットの装飾品で、左右対称に飾ります。こちらもコンパクトな上置き型の仏壇には、あまり使用されません。
常花(じょうか)
常花は、浄土に咲く蓮の花を模した金属製の造花です。極楽浄土を象徴している常花ですが、浄土真宗では生花をお供えするべきという考えがあるため常花は飾りません。
霊供膳(れいぐぜん・りょうぐぜん)
霊供膳は、供養の際に用いられる精進料理用の器セットです。ご飯や汁物などを盛る専用の器が一式揃っていて、特別な供養のために使用されます。ただし、浄土真宗では霊供膳を使用しません。


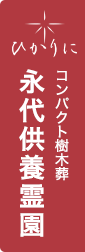
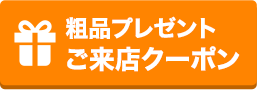
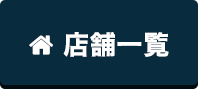
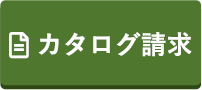







クチコミ件数
156件平均評価
4.9