いままで、仏壇は長男が引き継ぐことが当たり前とされてきましたが、核家族が増えた現代ではその常識が変化しつつあります。親や子ども、それぞれが独立して生活している場合、親が死んだあとの仏壇はどのように扱えばよいのでしょうか。
今回の記事では、親が死んだあとの仏壇の後継者選びのポイントや引き継ぎ後の管理方法についてご紹介します。
目次
昔から仏壇は代々長男が引き継ぐものだった
親が死んだ後の仏壇は、昔は長男が引き継ぐのが当たり前でした。しかし、 現代の考え方では長男・長女だからといって仏壇を引き継がなければならないということはありません。兄弟姉妹をはじめとする親族同士で話し合いを行い、引き受ける者を決めるのが一般的です。
そのほかにも、親の遺言や地方の慣習、家庭裁判所の決定によって決められることもあります。家族での話し合いだけでは難しい場合は、専門家の助言を活用するとよいでしょう。
仏壇の後継者を選ぶ際の4つのポイント

ここでは、仏壇の引き継ぎを決める際の4つのポイントをご紹介します。
① 祭祀継承者に該当するかどうか
まずは、誰が「祭祀継承者」に該当するのかを確認しましょう。祭祀継承者とは、故人が生前に口頭もしくは遺言書にて指定した人物のことを指します。まずは祭祀継承者に該当する方がいるかどうかを法的な手続きに基づいて確認するとよいでしょう。
なお、そのような指定がない場合は、優先的に直系子孫もしくはその配偶者が引き継ぐことが一般的とされています。
② 信仰心があるかどうか
仏壇は、仏さまやご先祖さまを祀るための大切なものです。もし後継者に信仰心がなく、仏壇や供養に関心がなければ、引き継ぎを無事行えたとしてもその後の管理を続けていくことが難しくなるでしょう。そのため、後継者に信仰心や関心があるかどうかも重要なポイントとなります。
仏壇を引き継ぐ人物は、仏さまやご先祖さまを敬う心を持ち、仏壇を置く意味や自分の役割を理解している方が望ましいでしょう。
③ 仏壇を管理し、維持できるかどうか
仏壇はつくりが繊細でデリケートなため、適切な管理が必要です。長い年月管理するなかで、ときには修復が必要になることもあるかもしれません。仏壇を引き継ぐ方は、今後そのような出費が必要となる可能性も念頭に入れる必要があります。仏壇を管理し、状態を維持することに責任感を持つ方を選ぶとよいでしょう。
④ 家の歴史・伝統を尊重するかどうか
家の歴史・伝統を尊重する人物かどうかも重要なポイントです。仏壇は先祖代々を供養する場所であるとともに、家の歴史や伝統の象徴となります。そのため、それらを尊重し後世に繋いでいくことの重要性を理解している方が引き継ぐことが望ましいです。
仏壇を引き継ぐ場合

仏壇の引き継ぎは多くの場合、「別の家で引き継ぐ・位牌をわける・仏壇を処分する」の3つの選択肢にわかれます。ここでは、それぞれの方法についてご紹介します。
仏壇を移動し、別の家で引き継ぐ
仏壇を現在の家から出す場合は「魂抜き」、別の家に入れる場合は「魂入れ」の儀式が必要です。魂抜きは主に仏壇の移動や処分の前に行われる儀式のことで、僧侶の読経により仏像や掛軸、位牌などに宿った魂を抜きます。魂入れはその逆です。
魂抜きは「お性根抜き(おしょうねぬき)」や「閉眼供養(へいげんくよう)」とも呼ばれ、魂入れは「入魂開眼供養(かいげんくよう)」や「お性根入れ(おしょうねいれ)」とも呼ばれています。
なお、仏壇本体はお祀りするための場所であり魂は宿っていないと考えられているため、仏壇本体に対する魂抜きは不要である場合が多いです。ただし、お寺や地域の考えによっては、仏壇に対する魂抜き・魂入れが必要となるケースもあるため、事前に必ず確認をしましょう。
仏壇を移動する際にかかる費用相場
仏壇を移動する際にかかる費用総額は、平均して2万円弱~15万円程度になることが多く、その内訳は「魂入れ・魂抜きのお布施代」と「仏壇の移動代」の2つです。費用相場に大きな開きが生じる理由は、お寺に渡すお布施代や仏壇を移動する距離や依頼先によって費用が大きく異なるためです。
仏壇を移動する方法
仏壇を移動する方法は大きくわけて3つです。
①仏壇仏具の専門店に依頼する
仏壇の移動サービスを行っている仏壇仏具の専門店の場合は、仏壇の梱包はもちろん、移動先での設置まで行ってくれることもあります。自分一人で設置を行うのが不安な方にはおすすめです。ただし、仏壇の状態や移動先によっては依頼できないケースもあります。
②運送会社や引越し業者に依頼する
大手の運送会社や引越し業者にも仏壇の移動を依頼できます。ただし、仏壇の材質や状態によってはキズがついたり破損したりする危険もあるため、安心して任せられるかどうかを事前に確認することが重要です。面倒であっても必ず複数の業者を比較検討しましょう。
なお、なかには魂抜きをしていないと断られるケースもあるため、魂抜きを行わずに移動したいと考えている場合は注意が必要です。
③自分で移動する
仏壇を自家用車に載せて運ぶ方法もあります。その際、仏具はすべて取り出して別で梱包を行い、仏壇は倒れないようしっかり固定しましょう。この方法の場合、自分の都合の良いタイミングで移動を行えたり、費用が非常に安く済んだりするというメリットがあります。
ただし、仏壇はかなりの重量があるため労力が必要となることや、素人が仏壇を扱うためキズや破損の危険も生じます。できれば仏壇仏具の専門店や業者へ依頼する方が安全に移動できるでしょう。
一つの家に仏壇を二つ置く場合
現在、自分の家にある仏壇と、実家で使用していた仏壇の宗派が異なる場合は、一つの家に仏壇を二つ置いても問題ありません。ただし、仏壇を置く向きが決まっている宗派もあるため、置き場所への配慮は必要です。一方で、一つの家に仏壇が二つあることをNGとするお寺や宗派もあるため、その場合はどちらかの仏壇を処分しなければいけません。なお、宗派が同じ場合は仏壇を一つにまとめることが可能です。
仏壇を引き継がない場合

引き継ぎたくとも仏壇を置くスペースがなかったり、宗教上の理由で引き継げなかったりなどさまざまな状況が考えられます。また、なかには「仏壇を継承したくない」と考える方もおられることでしょう。
そういった場合は、下記の方法があります。
・仏壇を親戚に引き継いでもらう
・仏壇を処分し、位牌だけ親戚の仏壇に引き取ってもらう
・仏壇を処分し、位牌もお寺や霊場で永代供養する
まずは親戚に相談し、難しい場合は付き合いのあるお寺に永代供養の相談をしてみましょう。もし、お寺と付き合いがない場合は仏壇仏具店に相談してみてください。
仏壇を処分する方法は4つ
ここでは、仏壇の処分方法についてご紹介します。
処分方法を決める
仏壇の処分方法は、以下の4つが挙げられます。
①仏壇店に引き取ってもらう
仏壇の処分方法として最も一般的なのが、仏壇仏具の専門店に引き取ってもらう方法です。仏具を扱うプロである専門店であれば、安心して仏壇を任せられるでしょう。なお、その場合、仏壇と一緒に香炉や花立、位牌などの仏具も引き取ってもらえることが多いです。
②お寺に引き取ってもらう
お寺に引き取ってもらう方法もありますが、仏壇の引き取りを行っているかどうかは確認が必要です。引き取りを行っている場合であっても、仏壇の大きさによっては断られることもあるので事前に確認しておきましょう。
③不用品回収業者やリサイクル業者に依頼する
不用品回収業者やリサイクル業者に仏壇を処分してもらう方法もあります。仏壇引き取りの専門業者もあるので調べてみましょう。希少な木材が使用されている仏壇に関しては、引き取ってもらえる可能性が高くなります。
④自分でゴミに出す
自分で仏壇をゴミに出して処分する方法もあります。仏壇の解体ができれば、燃えるゴミとして処理可能です。もし、仏壇の解体が難しい場合はお住いの自治体に依頼し、粗大ゴミとして回収してもらいましょう。
閉眼供養を行う
仏壇を処分する場合も僧侶に依頼して、魂抜きを行います。この魂抜きを行わずに仏壇を処分することは罰当たりだと考えられているため、魂抜きを済ませていない場合は引き取りを拒否している業者も多くあります。仏壇を処分する前には、必ず魂抜きをしてもらいましょう。
仏壇を置かない場合の供養方法

現代では仏壇を持たないという選択肢も多く広まっています。ここでは、仏壇を持たない場合のご先祖さまの供養方法についてご紹介します。
手元供養をする
手元供養とは、遺骨を手元に置いて供養する方法のことです。この方法だとスペースがそこまで必要ではないため、大きな仏壇が置けない場合に選ばれています。部屋の一部に供養のためのスペースをつくったり、遺影と仏具を飾ったりなど、方法はさまざまなのでその家の状況によって供養方法を選択することが可能です。
位牌のみを祀る
仏壇を処分した場合、位牌のみを祀る方法もあります。位牌には魂が込められているため、位牌に手を合わせることで供養することが可能です。位牌は小さいため、供養のための場所を取らないのがメリットだといえるでしょう。


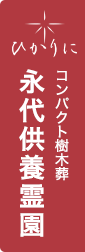
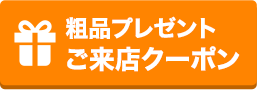
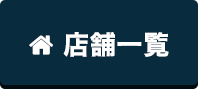
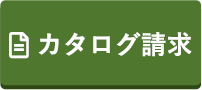







クチコミ件数
156件平均評価
4.9