お供え物の定番であるお線香やお花以外にお菓子をお供えする際、「これはお供え物として出して問題ないのか」と疑問に思うことはありませんか? 実は、お菓子のなかにはお供え物に適していないものがあります。お供え物を選ぶ際には基本的なマナーに沿い、仏さまやご先祖さまに失礼がないように意識しましょう。
今回の記事では、仏壇へのお供え物として適しているお菓子、反対に不適切なお菓子とその理由を解説します。
目次
仏壇へのお供えの基本は「五供」

仏教においては「五供(ごくう)」と呼ばれる考え方があり、主にお供え物に使われるのは、以下の5種類です。
お線香
仏さまやご先祖さまは香りを召し上がると考えられており、また仏壇にお線香の香りはお供えをする人の心と体を浄化する効果があるとも言われています。
お線香については、こちらの記事もご参考になさってください。
お仏壇へ線香をあげる理由や注意点を徹底解説
仏花
仏壇にお供えする仏花は、お線香と同じく仏さまやご先祖さまにとってのお食事になる一方で、お花の美しさが供養する側の心を癒やすとされています。
お供えするお花は、四十九日までは菊や百合、カーネーションなどがおすすめです。忌明け以降は、故人や家族の好みで選ぶとよいでしょう。ただし、棘があるお花やツルのあるお花、においが強すぎるお花は供花にはふさわしくありません。
仏花については、こちらの記事もご参考になさってください。
仏花と墓花は何が違う?仏花のタブーや飾り方もご紹介
ろうそく
仏壇にお供えするろうそくは、灯燭(とうしょく)とも呼ばれています。ろうそくは主にお線香をつける際に使われていますが、それ以外にも二つの役割があるとされています。
仏教の教えでは、ろうそくの炎は仏さまの「智慧」と「慈悲」を表します。暗闇を照らす「智慧」で人々の心の闇や無知を照らし、炎の熱で温める「慈悲」で人々を慰め救済すると考えられているのです。また、ろうそくの光は浄土へ旅立つための道しるべであり、お参りをする人が「ここにいます」と伝える役割も持っています。
水
仏教では、仏さまやご先祖さまも生きている人と同じように乾いた喉を潤すために水を飲むと考えられているため、仏壇に水は不可欠です。また、水には清めの効果があり、水で穢れ(けがれ)を落とすとされています。そのため、仏壇の水はこまめに交換するようにしましょう。
仏飯(ぶっぱん)
仏壇にお供えするご飯は、「仏飯(ぶっぱん)」もしくは「飲食(おんじき)」と呼ばれています。仏飯は、ご飯以外にお菓子や果物なども添えるのが一般的です。
お供えしたご飯を下げた後は冷める前に家族でいただくのが一般的ですが、無理に食べなくても問題ありません。なお、衛生面を考慮してご飯にラップをかけるのは失礼になるため、控えましょう。
お供え物におすすめのお菓子

お供え物というと和菓子のイメージが強いかもしれませんが、近年では和菓子にこだわらず洋菓子もお供え物として用いられています。ここでは、お供え物におすすめのお菓子をご紹介します。
落雁(らくがん)などの砂糖菓子
お供え物として定番のお菓子は、砂糖菓子の落雁です。落雁は米粉や大豆粉、蕎麦粉などに砂糖や水あめを加えて練り、木型に押し固めて乾燥させた和菓子です。水分量が少なく日持ちがよいことから、お供え物としてよく用いられています。
また、落雁はお供え後にそのまま食べる以外に、砂糖の代わりとしてコーヒーや紅茶に入れたり、料理やお菓子づくりに再利用できたりするなど、アレンジしやすいところもポイントです。
クッキーやマドレーヌなどの焼き菓子
クッキーやビスケット、マドレーヌ、ミニケーキなどは水分量が少なく賞味期限が長いものが多いため、お供え物に向いています。また、お菓子の種類が豊富で、スーパーなどでも取り扱いがあるため手に入りやすいお菓子です。
ただし、なかには日持ちしないものもあるため、賞味期限をよく見て選びましょう。
羊羹やまんじゅうなどの生菓子
生菓子は羊羹やまんじゅうのほかに、最中、おはぎ、どらやき、ゼリー、カステラなどがあります。これらのお菓子は焼き菓子に比べて水分量が多いものの、密封容器に入れられていたり真空になっていたりして保存がきくものが多いです。なかでも羊羹やゼリーは、夏場の暑い時期でも常温保存が可能でおすすめの生菓子だといえるでしょう。
おかきや煎餅などの米菓
お供え物といえば砂糖をつかった甘いお菓子をイメージする方が多いかもしれませんが、おかきやあられ、煎餅などの米菓もお供え物として人気のお菓子です。とくに個包装の米菓であれば分けやすく、持ち帰ってもらいやすいためおすすめです。
仏壇のお供え物としてNGなもの
仏壇へのお供え物として適していないものがあります。たとえ故人が生前に好んで食べていたものであったとしても、お供え物としてはタブーとなることもあるため注意が必要です。ここでは、お供え物にふさわしくない食品について解説します。
肉や生魚など
肉や魚、卵、乳製品関連の品物はお供え物に適していません。仏教では殺生を禁じていることにくわえて、「四つ足生臭もの※」とも呼ばれているためタブーにあたります。
※四足歩行の動物の肉(牛肉、豚肉、鶏肉など)や、生魚(刺身や寿司など)を指す。
とはいえ、故人が生前に肉や魚を好んでいた場合、お供えしてあげたい気持ちがあると思います。その場合は、調理したものをご飯と一緒にお供えするようにしましょう。
においが強すぎるもの
仏教では、修行の妨げにならないように「五辛(ごしん)」と呼ばれる農産物を控えています。五辛は、ニンニクやニラ、ネギ、らっきょう、はじかみを指します。仏さまやご先祖さまは香りを召し上がられるため、五辛が使われている料理は避けなければいけません。
傷みやすいもの
お供え物を選ぶ際、傷みやすいものは避けましょう。果物の場合は、みかんやぶどう、桃、いちごなどは傷みやすいため避けた方が無難です。りんごやバナナはお供え物として選ばれることが多いですが、りんごはエチレンガスを発生させて他の果物の追熟を進めるため、置き方には注意が必要です。
また、生クリームを使ったケーキなどは、常温保存ができず日持ちしないため、お供え物には向いていません。それでも、故人の好物だったので供えたいという場合は、手を合わせた後にすぐ下げるようにしましょう。
お供え物は「傷む前に下げる」のが基本
お供え物には「お供えとして置いておく期間」というのは明確に決められていませんが、基本的にはお供え物が傷む前に下げるのがマナーです。そのため、傷みやすいものや賞味期限が短いものに関しては、手を合わせた後すぐに下げても問題ありません。
逆に、傷んでしまったり腐ってしまったりしているお供え物をいつまでも置いておくと、仏さまやご先祖さまに対して失礼にあたります。下げた後のお供え物については、感謝をしながら家族で食べるようにしましょう。


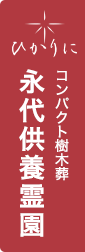
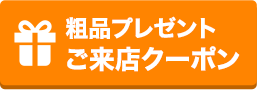
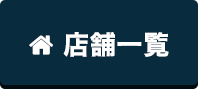
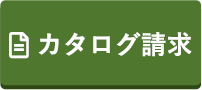







クチコミ件数
156件平均評価
4.9