苫小牧周辺の一般的なお盆は8月13日~16日までの「月遅れ盆」で行われ、お盆期間中はお仏壇の周辺に盆棚などを設置して装飾を施します。「お盆は飾り付けをするもの」という認識をされている方が大半だと思いますが、「いつから飾り付けが必要で、どのタイミングで片づけるのか」「どんなお盆飾りが必要なのか」など、具体的に理解している方は実は少ないかもしれません。
この記事では、お盆飾りの期間や飾り方、それぞれの意味などをご紹介しますので、ぜひご参考にしてください。
目次
お盆飾りの期間はいつからいつまで?
お盆飾りは、お盆の期間中(苫小牧は8月13日~16日の4日間)にお飾りをするのが一般的です。前日になって慌てないよう8月に入ったタイミングから余裕をもって準備し始め、12日の夕方または13日の朝までに飾り付けを終えるのが望ましいです。
ただし、新盆を迎える際や親戚が事前にお参りに来たりする際には、早めに飾り付けをしてもよいとされています。なお、盆提灯は8月上旬から飾っても問題ありません。
片付けは遅くとも翌日までに終わらせる
お盆飾りの片付けは、送り火(お盆に帰ってきたご先祖様の霊を彼岸へお見送りするために焚かれる火)後に行うため、お盆最終日の16日の夜か、当日が難しければ、17日までに片付けましょう。
お盆飾りの基本的な飾り方
お盆の期間中は、祭壇を使ってお盆飾りをするのが一般的です。ここでは、お盆飾りの基本的な飾り方についてご紹介します。
お盆飾りは盆棚を使用する
お盆飾りで使用する祭壇のことを「盆棚(ぼんだな)」もしくは「精霊棚(しょうりょうだな)」と呼び、ここに盆提灯などのお供え物を並べていきます。ご先祖様はこのお位牌を依代(よりしろ)として帰ってこられるため、盆棚の最上段にはお位牌をおまつりしましょう。
なお、盆棚は二段~三段のものを準備するのが一般的ですが、近年ではスペースの関係等で一段飾りにすることも多くなっています。
盆棚はどこで買える?
盆棚は、仏壇専門店やホームセンターなどで購入が可能です。または、ご葬儀の際に使用した祭壇をそのまま盆棚として利用する方も多くいます。また、近年の住宅事情からスペースの確保が難しい場合は、部屋の一角にスペースをつくって小規模で飾ったり、経机(きょうづくえ)やミニテーブルを盆棚の代わりとして利用したりする方も増えています。
お盆飾りに必要なものと意味・飾り方
ここでは、一般的に用いられるお盆飾りをご紹介します。ただし、お盆飾りの意味や飾り方については、宗派や地域によって異なるため注意が必要です。
盆棚
盆棚はお仏壇のそばに置かれる祭壇のことを指します。二段~三段の盆棚をお仏壇の横や前に設置するのが正式な設置方法ですが、近年では別の方法で盆棚を設ける方も増えています。
盆提灯(ぼんちょうちん)
ご先祖様の魂が彼岸から迷わず家まで帰ってくるための「迎え火」としての役割と、お盆の終わりにあの世へ魂を送り出す「送り火」としての役割を持つ盆提灯。盆提灯には植物や家紋などが描かれており、置くタイプと吊るすタイプの2種類があります。
盆提灯は、お盆に入る約2週間前から飾り始めて、お盆明け以降に片付けるのが一般的です。たとえば、7月盆の地域の場合は、7月1日頃に飾り始め7月16日以降に片付けをします。苫小牧のように8月盆の地域の場合は、8月1日頃から飾り始め8月17日以降に片付けるとよいでしょう。
初盆(新盆)の場合は白提灯を飾る
初盆(新盆)では、四十九日後に初めて故人があの世から家に帰ってきます。その故人の魂が道中で迷わないよう「白紋天(しろもんてん)」と呼ばれる、紋様の入った吊り下げ型の白提灯を家の軒下に設置するのが一般的です。
集合住宅の場合など軒下に吊り下げるのが難しい場合は、カーテンレールに吊るして室内で飾ることもあります。
真菰(まこも)・蓮の葉
真菰は、「お釈迦様がその上で病人を治療した」といういわれを持つゴザです。盆飾りは、基本的に盆棚の上に真菰のゴザを敷き、その上に蓮の葉や精霊馬、季節の野菜・果物などのお供え物を置きます。生前、故人の好んだものを置くのもよいでしょう。
精霊馬(しょうりょううま)
精霊馬はあの世とこの世を移動する際のご先祖様の乗り物で、キュウリを馬、茄子を牛に見立ててかたどっています。この世に帰ってくるときは早く帰れるよう馬を使い、あの世に戻るときには牛を使ってゆっくり帰ると言われています。一般的には夏野菜を使う精霊馬が知られていますが、和紙など別の材料で代用される場合もあります。
鬼灯(ほおずき)
がく(花の付け根)の形が提灯に似ているため、鬼灯は精霊馬で帰ってくる際に道を照らす灯かりになると言われており、盆提灯や迎え火と同じくお盆飾りで欠かせない飾り物のひとつです。鬼灯は真菰の上で他のお供え物と一緒に置いたり、花瓶に生けたり、盆棚の脚にくくりつけたり、吊るしたりして飾ります。
そうめん
お盆飾りによく用いられるそうめんは、茹でずに束のまま真菰の上に置くか、お皿の上に置いてお供えするのが一般的ですが、そうめんを茹でた状態でお供えする地域もあります。そうめんをお盆飾りとするいわれは、「精霊馬の手綱とするため」や「あの世へ戻る際に持って行くお土産や荷物をまとめるため」、「細く長く幸せが続くよう願うため」など諸説あります。
水の子・閼伽水(あかみず)
地域や宗派によっては、お盆飾りに「水の子」を飾ることもあります。水の子とは、蓮の葉の上にさいの目に切ったキュウリと茄子、洗った米を混ぜたものを乗せ、それを閼伽水(蓮の葉やみそはぎで清めた水)に浸したものです。水の子のいわれも諸説あり、「ご先祖様の喉を潤すため」や「餓鬼道に落ちた無縁仏へのお供えのため」などと言われています。
麻がら(おがら)
麻がらは、迎え火・送り火の際に使用する棒状のものです。麻がらを玄関先で燃やし煙を出すことで、その煙に乗ってご先祖様があの世から帰ってくると言われています。その他にも麻がらは精霊馬の脚や箸として用いる場合もあります。
迎え火・送り火をする際は、ほうろく皿の上に麻がらをのせて庭や玄関先で燃やします。火の始末にはくれぐれもご注意ください。
みそはぎ
「みそはぎ」は8月半ばに盛りを迎える多年草で、赤紫色のフリルの様な花弁が特長の花です。みそはぎは、餓鬼道に落ちた人の喉を潤すための供養として用いられることがあります。地域によっては、お参りの際にみそはぎを水を含ませて水の子に振りかけることもあります。
十三仏(じゅうさんぶつ)
お盆だけではなく、法事や彼岸などの仏事では「十三仏」と呼ばれる掛け軸をお仏壇の近くに飾ります。十三仏とは、以下の13の仏様を指します。
・初七日:不動明王
・二七日:釈迦如来
・三七日:文殊菩薩
・四七日:普賢菩薩
・五七日:地蔵菩薩
・六七日:弥勒菩薩
・七七日(四十九日):薬師如来
・百カ日:観音菩薩
・一周忌:勢至菩薩
・三回忌:阿弥陀如来
・七回忌:阿閦如来
・十三回忌:大日如来
・三十三回忌:虚空蔵菩薩
それぞれの仏様には役割があり、十三仏を飾ることで故人を守護してくれると考えられています。また、十三仏の掛け軸には「故人が早く浄土に行けるように」という願いも込められています。
お盆飾りの片付け・使い回しについて
昔は「仏事で一度使用したものは使い回しをしていけない」という教えがありましたが、近年ではあまりこだわらなくなりました。ここでは、それぞれの片付け方をご紹介します。

盆提灯
盆提灯は、ほこりや汚れを取り丁寧に手入れをしてから収納し、翌年も使えるようであれば使っても構いません。絹で作られた盆提灯は虫に食われやすいので、防虫剤と一緒に箱に保管するようにすると長持ちします。
白提灯
初盆用の白提灯の使用はその年限りです。初盆を終えたらお焚き上げなど供養をしてから処分しましょう。
精霊馬・蓮の葉
精霊馬や蓮の葉を生のもので作っている場合は、その年限りで処分します。プラスチックなどで作られているレプリカであれば、翌年以降も使って問題ありません。
真菰
真菰は、地域によっては「水に濡れたものは処分すべき」としているところもありますが、そうでなければ少々濡れたり汚れたりした程度であれば、翌年も使用できます。その際は、汚れを拭き、清めた後にしっかりと乾燥させましょう。
その他のお供え物
果物やお菓子などの食べ物をお供えした場合、食べられるものはできるだけ家族でいただきましょう。食べきれないものやお花については、庭に埋めるかお焚き上げをします。それが難しい場合は、塩で清めてから白い半紙などに包み、清めてから可燃ごみとして出しても問題ありません。
お盆時のお仏壇へのお飾りについて
お盆中は盆棚がメインなので、お仏壇に特別なお飾りをする必要はありません。また、お参りも盆棚前で行うだけで問題ありません。
ただし、もしお仏壇と盆棚を違う部屋に配置している場合は、お仏壇にも手を合わせて感謝の気持ちを伝えるようにしましょう。なお、お盆期間中に訪問客が来る可能性もあるので、お仏壇周りはきれいに掃除しておくと安心です。
お得な「お盆感謝セール」を開催中!
大師堂仏壇店3店舗では、7月1日(火)~8月20日(水)まで『お盆感謝セール』を開催中です。
セール中は、
・線香、ろうそく:20%OFF
・お念珠、うでわ念珠:20%OFF
・ミニ骨壺、遺骨ペンダント:10%OFF にてご提供。
また、お盆提灯(置き提灯・吊り提灯・創作提灯)も特別価格にてご用意しています。昔ながらの提灯はもちろん、現代風でおしゃれなデザインの提灯や省スペース提灯も豊富に取り揃えているので、きっとお気に入りが見つかるはず。この機会にお盆提灯のご購入を検討してみてはいかがでしょうか?
※提灯に家紋を入れる場合は7月25日までにご用命ください。


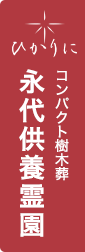
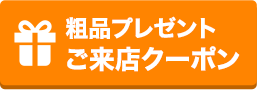
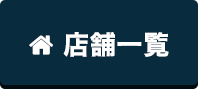
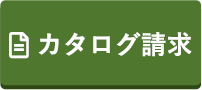







クチコミ件数
156件平均評価
4.9