日本には多くの宗派が存在しますが、それぞれの宗派によってお仏壇の選び方が異なることをご存知でしょうか。そのため、お仏壇の購入にあたって最初に行うべきは、ご自身の家の宗派の確認です。お仏壇を購入してしまってから菩提寺や親族から指摘されることがないよう、しっかりと確認したうえで購入しましょう。
この記事では、真言宗・曹洞宗・臨済宗のお仏壇の種類、仏具や仏像などの選び方などをご紹介します。
目次
【宗派別】お仏壇・仏具・お位牌・仏像・掛け軸の選び方
お仏壇には、宗派によりさまざまな違いがあります。それぞれの宗教ごとのお仏壇や仏具、お位牌、仏像、掛け軸の選び方について解説します。
真言宗(しんごんしゅう)
お仏壇の選び方
真言宗のお仏壇では「このお仏壇でなければいけない」といった決まりは特になく、唐木仏壇でもモダン仏壇でも問題ありません。ただし、浄土真宗などで使われる金仏壇は使用しないので注意しましょう。
▼お仏壇の商品ページはこちら。
https://taishido-b.jp/butsudan/
仏具の選び方
真言宗の仏具は、花立・火立・香炉の「三具足」、もしくは花立・火立・香炉・仏器・茶湯器の「五具足」です。基本的なお祀りの場合は三具足、正式にお祀りしたい場合は五具足を用います。また、各家の供養の仕方に合わせて必要であれば、ご飯を盛る仏飯器、水やお茶を入れる茶陶器、おりんなどを揃えましょう。
▼仏具の商品ページはこちら。
https://taishido-b.jp/item/butsugu
お位牌の選び方
「人間は生きながらにして仏になることが可能」と説く「即身成仏」を教えの中心に据える真言宗ですが、ほかの宗派と同じように故人の魂を入れるためのお位牌をお仏壇に祀ります。
ほとんどの宗派には「どのお位牌でなければいけない」のような特別な決まりはありません。お位牌には、伝統的な唐木位牌、塗位牌、モダン位牌などさまざまな素材や色、デザインのものがあるので、故人が好みそうなものを選ぶとよいでしょう。また、お仏壇の雰囲気に合わせたり、置く部屋の雰囲気に合わせたりするのもポイントです。
▼お位牌の商品ページはこちら。
https://taishido-b.jp/item/oihai
仏像・掛け軸の選び方
真言宗の場合、ご本尊は大日如来を祀りますが、もしご自身が信仰している仏様がある場合は、そちらを祀っても問題ありません。これは、「すべての神仏の元は大日如来で、そのほかの仏は大日如来が姿・形を変えた化身である」という考えがあるためです。実際に、日本にある真言宗の各寺のご本尊には、お不動様や観音様、お地蔵様などさまざまな仏様が祀られています。
とはいえ、一般家庭においては、ご本尊に大日如来を祀り、右側に弘法大師、左側に不動明王もしくは興教大師を祀るのが基本となっています。
曹洞宗(そうとうしゅう)
お仏壇の選び方
曹洞宗のお仏壇選びについても特に決まりはありませんが、伝統的な唐木仏壇かモダン仏壇を使用するのが一般的です。ただし、浄土真宗などで使用される金仏壇はほとんど使用しません。
▼お仏壇の商品ページはこちら。
https://taishido-b.jp/butsudan/
仏具の選び方
曹洞宗では仏具について明確な決まりがありません。そのため、基本となる花立・火立・香炉の「三具足」、もしくは花立・火立・香炉・仏器・茶湯器の「五具足」を使用します。基本的なお祀りの場合は三具足、正式にお祀りしたい場合は五具足を用いましょう。それに線香差しやおりん、打敷、灯篭、経机などを置くことで本格的な装いになります。
▼仏具の商品ページはこちら。
https://taishido-b.jp/item/butsugu
お位牌の選び方
ほとんどの宗派には「どのお位牌でなければいけない」のような特別な決まりはありません。お位牌には、伝統的な唐木位牌、塗位牌、モダン位牌などさまざまな素材や色、デザインのものがあるので、故人が好みそうなものを選ぶとよいでしょう。また、お仏壇の雰囲気に合わせたり、置く部屋の雰囲気に合わせたりするのもポイントです。
▼お位牌の商品ページはこちら。
https://taishido-b.jp/item/oihai
仏像・掛け軸の選び方
曹洞宗は仏教の開祖である「釈迦如来」がご本尊です。ただし、曹洞宗は基本的には各寺院の考え方が反映されるため、寺院によっては阿弥陀如来や観音菩薩をご本尊として祀るケースもあります。仏像はあくまでも仏心の象徴であるため、ご縁のある仏様を祀ればよいという考えなのです。
ただし、その脇に配置される脇侍(仏様の両脇につき添いサポートする存在)には決まりがあります。一般家庭のお仏壇では「一仏両祖の三尊仏」の形で中央に釈迦如来、右側に承陽大師、左側に常済大師を祀りましょう。
なお、同じ曹洞宗でも一部の寺院では脇侍が右左反対のケースもあるため、心配な場合は所属する寺院に聞いてみてください。
臨済宗
お仏壇の選び方
臨済宗のお仏壇選びについても特に決まりはありませんが、伝統的な唐木仏壇かモダン仏壇を使用するのが一般的です。
ただし、臨済宗は宗派が細かく分かれていて、地域や寺院ごとに選び方や飾り方が異なるケースがあります。数ある臨済宗の宗派の中で中心となるのが「妙心寺派」であるため、臨済宗=妙心寺派を指す場合が多いので注意しましょう。
▼お仏壇の商品ページはこちら。
https://taishido-b.jp/butsudan/
仏具の選び方
臨済宗での仏具の選び方も基本的には決まりがありません。基本的な三具足(花立・火立・香炉)や、五具足(花立・火立・香炉・仏器・茶湯器)を使用しましょう。これに線香差しやマッチ消し、おりんを付けた仏具を祀るのが一般的です。
▼仏具の商品ページはこちら。
https://taishido-b.jp/item/butsugu
お位牌の選び方
臨済宗も、お位牌の種類やデザインについて決まりはありません。故人の好みそうなお位牌や、お仏壇に似合うお位牌など自由に選びましょう
▼お位牌の商品ページはこちら。
https://taishido-b.jp/item/oihai
仏像・掛け軸の選び方
現在、臨済宗は14派に分かれていますが、すべてご本尊は釈迦如来です。ただし、両脇の脇侍はそれぞれで異なります。
臨済宗全般:脇侍左)普賢菩薩、脇侍右)文殊菩薩
妙心寺派 :脇侍左)花園法皇、脇侍右)無相大師
建長寺派 :脇侍左)大覚禅師、脇侍右)達磨大師
円覚寺派 :脇侍左)佛光国師、脇侍右)達磨大師
南禅寺派 :脇侍左)大明国師、脇侍右)達磨大師
方広寺派 :脇侍左)聖鑑国師、脇侍右)達磨大師
永源寺派 :脇侍左)正燈国師、脇侍右)達磨大師
佛通寺派 :脇侍左)愚中禅師、脇侍右)達磨大師
東福寺派 :脇侍左)聖一国師、脇侍右)達磨大師
相国寺派 :脇侍左)普明国師、脇侍右)達磨大師
建仁寺派 :脇侍左)栄西禅師、脇侍右)達磨大師
天龍寺派 :脇侍左)夢窓国師、脇侍右)達磨大師
向嶽寺派 :脇侍左)大円禅師、脇侍右)達磨大師
大徳寺派 :脇侍左)大燈国師、脇侍右)達磨大師
国泰寺派 :脇侍左)妙意禅師、脇侍右)達磨大師
お得な「お盆感謝セール」を開催中!
大師堂お仏壇店3店舗では、7月1日(火)~8月20日(水)まで『お盆感謝セール』を開催中です。
セール中は、
・線香、ろうそく:20%OFF
・お念珠、うでわ念珠:20%OFF
・ミニ骨壺、遺骨ペンダント:10%OFF にてご提供。
お仏壇や仏具も豊富にラインナップしているので、きっとお気に入りが見つかるはず。この機会に、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか?


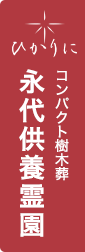
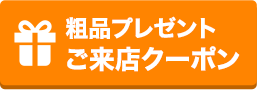
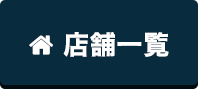
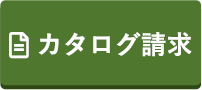







クチコミ件数
156件平均評価
4.9