お仏壇やお墓へのお参りに欠かせないお線香。みなさんは正しいお線香のあげ方をご存知でしょうか?なかには「身近な人の作法を見てお線香のあげ方を覚えた」という方も多いかもしれませんが、実はお線香のあげ方には正しい手順やマナーが存在します。
この記事では、お線香をあげる理由やあげる際の手順、注意点などについてご紹介しますので、ぜひ参考になさってください。
お線香をあげる理由

ここでは、お線香をあげる3つの理由をご紹介します。
1)四十九日まではお線香の香りが故人の食事になる
仏教では、亡くなってから四十九日法要までの間はお線香の香りが故人の食事であると考えられているため、法要まではお線香の火を絶やさないようにするのが一般的です。これは「食香(じきこう)」と呼ばれる考え方で、仏様もお線香の香りを食されると考えられています。
なお、仏教経典にも「死後の人間が食べるは匂いだけで、善行を行った死者は良い香りを食べる」と記されています。
2)四十九日後はお線香の煙で故人と心を通わせる
四十九日法要を終えたあとは、お線香の煙を通してあの世にいる仏様や故人の魂と心を通わせることができると考えられています。お線香をあげて手を合わせ、感謝の気持ちを伝えたり近況報告をしたりして故人に思いを馳せましょう。
3)お線香の香りで心身を清める
仏教は約2500年前のインドで開かれた宗教です。仏教においてお香は、不浄を払い心身を清める効果があるとされてきました。お仏壇で手を合わせる際にお線香をあげるのは、俗世で汚れた心身をお線香の香りで清める意味が込められているからです。ぜひ、お仏壇で手を合わせる際には、お線香の香りで穢れを払い、きれいになった心身で仏様や故人とつながりましょう。
お線香の種類
近年ではさまざまなお線香の種類が発売されていますが、お線香は大きく分けると「匂い線香」と「杉線香」があります。ここでは、それぞれの特長について解説します。
匂い線香
「匂い線香」は一般家庭で多く使われていて、よい香りが特長のお線香です。主な原材料はタブノキの皮粉で、それを乾燥させ粉末にしてから香木の白檀(びゃくだん)、沈香(じんこう)、伽羅(きゃら)などと香料、墨の粉末を調合しています。
近年では、マンションなどの集合住宅でも使いやすいよう、煙が少ないタイプのお線香も販売されています。
杉線香
「杉線香」は火をつけると煙がたくさん出るお線香で、安価で買える点が特長です。主に、寺院での行事やお墓参りなどで使用されています。原材料は杉の葉で、火をつけると杉の香りがしますが、この香りは匂い線香の香りとは異なります。
杉線香は室内で使うと煙感知器が反応する可能性があるため、屋外以外では使わない方がよいでしょう。
お線香をあげる際の手順
お線香のあげ方には、ある程度の手順が決められています。ここでは一般的な手順をご紹介します。
弔問先でお線香をあげるとき
宗派や地域の慣習によって違いはありますが、一般的な手順は以下の通りです。
- 数珠は房を下にして左手で持つ
※お線香をあげている間も左手に掛けたまま - お仏壇の前でご遺族に一礼する
※座布団がある場合は座布団の手前で一礼する - お仏壇の前もしくは座布団の上に座ってから遺影に向かい一礼する
- 合掌する
※宗教、地域によっては合掌がない場合もある - 備えつけのマッチに点火し、ろうそくに火を灯す
- お線香を持ち、ろうそくにかざして火をつける
※お線香の本数は次の章でご紹介します - お線香を持った手と反対の手で扇いで火を消す
- 香炉にお線香を立てる
※お線香の立て方は次の章でご紹介します - おりんを一度だけ鳴らす
※浄土真宗ではおりんを鳴らさない - 数珠を両手に掛けて合掌した後、数珠を左手に掛け直す
- 遺影に向かって深く一礼する
- ろうそく消しでろうそくの火を消す
※ろうそく消しがない場合は手で扇いで消す
※自分の次にお線香をあげる方が控えている場合は消さない - お仏壇の前から一歩離れ(座布団に座っている場合は座布団から降りる)ご遺族に向き直って一礼する
- 元の席へ戻る
弔問時の注意点
ご葬儀後に弔問する場合は、ご葬儀から4~5日経過してから四十九日法要までの間にしましょう。その場合、弔問に伺う前に必ずご遺族に許可を取ることが大切です。なお、香典をお断りされるご遺族もおられるため、香典を持参してよいかどうかもその際に確認しておきましょう。
弔問時の服装は、カジュアルな服や派手な服、喪服は避けるべきです。なるべく落ち着いたデザイン・色味の平服にし、数珠を持参しましょう。お供え物は高価すぎるものや生ものは避け、なるべく日持ちのするものを選びます。
自宅でお線香をあげるとき
一般的には、以下の流れでお線香をあげます。
- 左手に数珠を持ち、仏壇の正面に座る
- 遺影に一礼して合掌する
※仏壇の位置によっては立ったまま行うこともある
※宗教、地域によっては合掌がない場合もある - 備えつけのマッチに点火し、ろうそくに火を灯す
- お線香を持ち、ろうそくにかざして火をつける
※お線香の本数は次の章でご紹介します - お線香を持った手と反対の手で扇いで火を消す
- 香炉にお線香を立てる
※お線香の立て方は次の章でご紹介します - おりんを鳴らす
※浄土真宗ではおりんを鳴らさない - 数珠を両手に掛けて合掌した後、数珠を左手に掛け直す
- 遺影に向かって一礼する
- ろうそく消しでろうそくの火を消す
【宗派別】お線香の本数や立て方
お線香をあげる際のマナーは宗派によって異なりますが、故人の宗派に合うかたちでお線香をあげるとより丁寧な弔問となり、ご遺族も喜ばれることでしょう。もし宗派がはっきりとわからない場合は、一般的なお線香のあげ方で問題ありません。
真言宗
- お線香の本数:3本
- 立て方:手前に1本、祭壇側へ2本のお線香を立てる
浄土宗
- お線香の本数:1本~2本を二つ折りにし、全て点火する
- 立て方:香炉の中央に立てる
※他にお線香をあげる方がいる場合は端に立てる
浄土真宗本願寺派
- お線香の本数:1本を二つ折りにして2つにしたものに点火する
- 立て方:火が左横になるようお線香を香炉に寝かせる
※香炉が小さくて寝かせにくい場合は、香炉に合わせて2~4等分に折り寝かせる
浄土真宗大谷派
- お線香の本数:1本~2本を二つ折りにして両端に点火する
- 立て方:火が左横になるようお線香を香炉に寝かせる
臨済宗・曹洞宗・日蓮宗
- お線香の本数:1本に点火する
- 立て方:香炉の中央に立てる
※他にお線香をあげる方がいる場合は端に立てる
お線香をあげるときの注意点3つ
お線香をあげる際にご遺族に対して失礼にならないよう、一般的なマナーを把握しておきましょう。
他にお線香をあげる方がいる場合は香炉のスペースを空けておく
お線香をあげる方が複数人になる場合は、全員が香炉のスペースを使えるように配慮してお線香を立てましょう。
マッチやライターで直接お線香に火をつけない
マッチやライターで直接、お線香へ火をつける行為はタブーです。実はろうそくには、不浄を払って清める効果があると言われ、ろうそくは故人を極楽浄土へ旅立たせるための手引きであるという考え方があります。お仏壇では必ずろうそくに点火し、ろうそくの火からお線香へ火を灯すようにしましょう。
お線香の火を消す際は手で扇ぐ
お線香についた火を息で吹き消す行為はタブーです。仏教では「人の口は不浄のもの」とされているため、息を吹き掛ける行為は大変失礼にあたります。
また古来より日本では、灯かりを大切なものとして扱っていたため、お仏壇のろうそくの灯かりは仏様を照らす重要な役割があると考えられています。お線香に火を移す行為は、”灯かりをいただく”という意味合いも含まれているので、息を吹きかける行為は無作法にあたります。
お線香の火は必ず持っている手と反対の手で扇いで消しましょう。
お得な「お盆感謝セール」を開催中!
大師堂仏壇店3店舗では、7月1日(火)~8月20日(水)まで『お盆感謝セール』を開催中です。
セール中は、
・お線香、ろうそく:20%OFF
・お念珠、うでわ念珠:20%OFF
・ミニ骨壺、遺骨ペンダント:10%OFF にてご提供。
この機会にお気に入りのお線香を見つけてみてはいかがでしょうか?


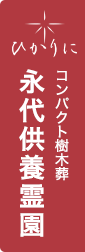
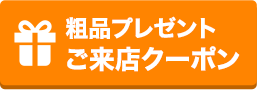
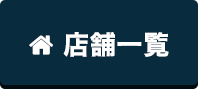
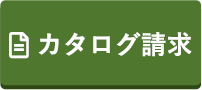
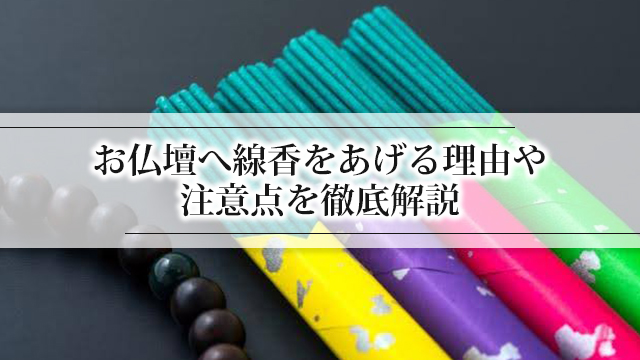






クチコミ件数
156件平均評価
4.9